「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.266
老後のために退職金で資産運用するときに考えておきたい3つのこと

悩む50代。
真剣な50代。
老後生活まで、後数年・・・。
そして、退職時期も見えてきた。
そんな50代からの相談が増えております。
多くの方が、中小企業の従業員として真面目に働いております。
そして、銀行預金しか経験がない。
投資は怖くてできない・・・。

近い将来に貰えるであろう退職金。
さあ、どのように運用すればいいのか?
そして、50代からでもできる老後資金の準備について。
退職金を運用する必要はあるか
最近、50代の男性から聞こえる言葉。
「どうせ、金利がつかないから、タンス預金でいいんじゃないの?」

果たして、そうでしょうか?
■物価は確実に上昇してます。

■消費税は増税になりました。

つまり、毎月同じ行動、同じ買い物をした場合を考えて下さい。
今まで、20万円で生活できたのが、24~25万円になる。

これが、1年、10年、20年と続けばどうなるのか・・・・。
つまり、仮に物価が平均2%上昇するなら、資産も2%以上増やさないと資産は減ります。
結果、『何もしない事が最大のリスク』になります。
では、今まで通りに、銀行定期預金で運用すると、どうなるか。
[2000万円を0.01%の銀行定期預金で運用]
10年間で2000万円→2002万円

では、平均3%の利回りで運用できると、どうなるか。
2000万円→2687万円

退職金での資産運用に外せない3つの考え方
年金の把握
老後生活資金の柱は公的年金です。
ですので、まずは、自分の年金がいくらもらえるのか。
老後の生活費は、いくらかかるのか。
そして、足りないのはいくらなのか。
幸い、50代の方は、年金定期便でおおよその把握はできます。
*50歳以上の方は、今と同じ収入で60歳まで働いた場合に65歳からもらう見込み額が表示されます。
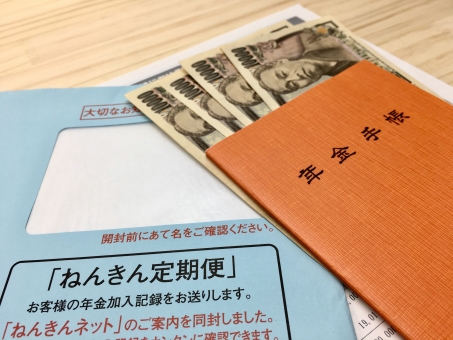
そして、何歳からもらうのか
多くの方は、勘違いされてませんか?
65歳からでしょ・・・。
現実は、60歳~70歳までの年齢で自己選択ができます。
■早く貰えば少なくなる。
(繰上げ請求)
■遅く貰えば、多く貰える。
(繰下げ請求)
例えば、基礎年金を満額貰える方。
*平成31年4月分からの年金額年額(月額)
■60歳で請求
→546,070円(45,505円)
■65歳で請求
→780,100円(65,008円)
■70歳で請求
→1,107,740円(92,311円)
ここでのポイントは65歳から70歳までの生き方です。
①健康が第一。
②なるべく働く、できれば75歳まで。
③早い時期から60歳から70歳までの生活費の確保。
つまり、70歳以降も大事ですが。
60歳から70歳までの生活費が大きなポイントです。
分散投資
退職時期が近くなると、注意が必要です。
様々な金融機関が、退職金の提案にやってきます。
それは、情報の仕入れという観点ではいい事です。
しかし、気をつけなればならない事があります。
1つの金融商品に集中しない事です。
基本的に金融機関の方は、自社の取扱商品のみ提案をします。
そして、少しでも多くの金額を期待します。

金利の高い時は、それで良かったのです。
しかし、今は違います。
完璧な金融商品など存在しません。
多少のリスクを覚悟しながら、確実なリターンの確保が必要な時代です。
ですので、分散投資が基本です。
では、何を分散するのか?
①金融商品
最低でも3つ以上の金融商品に分散。
②地域の分散
日本国だけはNG。世界に分散する。
③出口の時期
お金が使える時期を分散する。
出口戦略が大事です。
多くの方は、入口を重視します。
例えば、予想利回り、非課税、複利等々・・・。
しかし、更に大事な点は、出口戦略です。
つまり、いざ使いたい時にスムーズに使えるのか。
具体例を2つ。
■投資信託で、日経平均株価に連動するファンドで一括運用。
この場合、使いたい時に、日経平均株価が暴落していたらどうなるか?
残念ながら、資産を大幅に減らした状態で売却です。
*日経平均株価に連動するファンドの一部をご紹介です。
■ニッセイ日経225インデックスファンド
*SBI証券のつみたてNISA商品ラインナップから
・最高値:27,218円
*2018年10月2日
・最安値:6,798円
*2009年3月10日
差額が20,420円。

差額の20,420円で、どんな影響があるの?

投資の成績は
量(口数)×価格です。
例えば、口数が300の時点で換金をします。

■27,218円×300口
=8,165,400円
■ 6,798円×300口
=2,039,400円
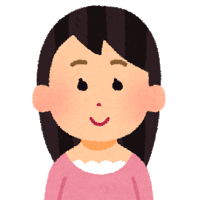
価額の差額は20,420円
実際、換金する際の差額は
4倍以上!
このように、株価の暴落で、大きな差額が発生する事もあります。
この事を想定しての事前対策が2つあります。
①株価暴落時は、1~2年我慢する。
②株価と相反する金融商品でも準備をしておく。
■外貨建一時払保険で一括運用。
この場合、満期時に円高が進んでいればどうなるか?
残念ながら、払込んだ元本が割れている可能性があります。
外貨建一時払いの場合は、入口、出口、両方で注意が必要です。
■入口(契約時):金利が3%未満の時はやらない。
*事前に損益分岐為替レートを確認する。
■出口(換金時):円高時は、すぐに換金しない。
*一時、外貨口座に置いておく。
つまり、使いたい時に株価が暴落しようが、円高になろうが、安心できる事前準備が必要です。
50代からできる老後資金準備
50代という年代は人生の中で、一番大変な時期かもしれません。
■住宅ローンの支払い
■お子様の教育資金
■自分自身の老後資金の準備
そして、昔の50代と今の50代。
投資の考え方も変わってきました。
一言すれば、守りの50代から攻めの50代です。
平均寿命も伸び、働ける年齢も伸びています。
つまり、50代でも20年~40年程度の長期運用が可能です。
一方で、増やしながら、取り崩す。
ですので、運用の選択肢は増えています。
使える手段は使う。
攻めの運用です。
そして、大事な点は、目的の明確化です。
例えば、こんな感じです。
①70歳以降、5年毎に老後資金として使う。

例えば、満期を70歳、75歳。
80歳85歳、90歳に設定するのです。
②万一の医療費の準備として使う。

例えば65歳以降は、いつでも使える準備を。
③住宅修繕費用として使う。

最初から、70歳時の住宅改修を決める。
つまり、目的により、使う時期も明確か不明確か違います。
ですので、金融商品の分散方法も知恵が必要です。
例えば、こんな感じです。
①毎月コツコツと積上げ、増やし続けるタイプ。
②ボーナスや退職金で一括運用するタイプ。
③元本は増やさず、定期的に配当を受け取るタイプ。
では、具体的にどんな金融商品があるのか。
■つみたてNISA
運用益の非課税枠を使いながら、いつでも換金できる。
■投資信託
世界株式を中心としたファンドを活用し、無期限に増やす。
■米国ゼロクーポン債
世界一安心できる投資手段。一括でも、積立でも投資が可能。
■投資信託毎月分配型
増やすのではなく、毎月分配金を受け取る。
■社債・劣後債
増やすのではなく、定期的に分配金を受け取る。
金融商品は日々変動しております。
併せて、金融商品には、メリットもあれば、デメリットもあります。
投資に不安な方、初心者の方は、個別相談もご活用下さい。

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。




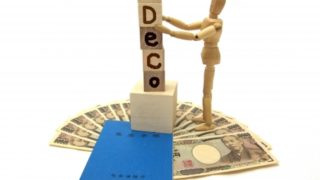


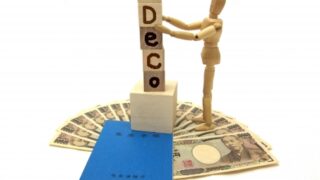



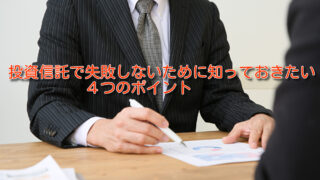

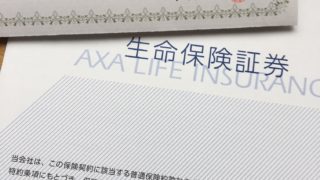

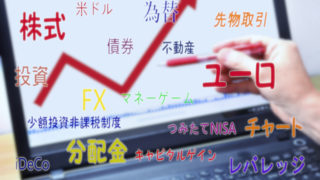
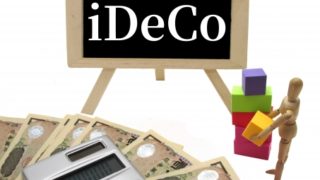









コメント