「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.260
投資信託を初めて買う初心者が勘違いする大事な基本を解説!

先日、知り合いの方が私に呟きました。
「最近、投資信託の調子が悪いんだよね・・・」

ちなみに、この方は50代の会社経営者で、今すぐお金が必要な方ではありません。
一方で、違う方は、こう呟きました。
「俺の投資信託は凄いよ、毎月必ず分配金が入るからね・・・」

ちなみに、この方は70代の方で、既に年金で生活をされている方です。
こういう話題になるとついつい話しも長くなるので、敢えて聞き流したのですが。
もしかしたら、勘違いされているのかな、と感じた呟きでした。
投資信託は、優れた金融商品です。
但し、使い方を誤れば損をする場合もあります。
そして、現実投資信託で失敗をされ、相談に来られる方もおります。
投資信託は、経験者でも勘違いをされてる方が多くおります。
そして、投資信託初心者がよく勘違いする基本について解説です。
投資信託には2つのタイプがある
まず、そもそも「投資信託」について分からない方は、下記の記事をご参照下さい。
投資信託とは?
まず、投資信託を始める目的が大事です。
大きく2つあります。
①お金を増やしたい。

②定期的に配当金を受け取りたい。

そして、目的に合わせるように、投資信託には2つのタイプがあります。
長い時間をかけて増やす
投資の基本でもあります。
長期・積立・分散
配当金を再投資して複利で増やす。

毎月分配型→毎月、配当金を受け取る
一方で、増やすのではない。
毎月、定期的に年金の不足分として使う。

ところが、先程の呟きに戻ります。
2人とも、実は毎月分配型のタイプで運用されてます。
まず、50代の会社経営者の方ですが、そもそも目的から外れているのです。
本来は、老後資金準備がしたいのに、毎月分配型を選択されてます。
理由は?
「銀行に勧められたから・・・・」

一方で、70代の方は、老後の生活費が目的なので大丈夫です。
と言いたいところですが・・・・。
本当に、大丈夫ですか??
毎月、配当金が出る事はいい事ですが、中味を理解されていますか?
配当金には2つの配当金があります
多くの方は、「配当金が毎月出る」という事実だけで判断されてます。
「なんと、いい商品なんだ」
「流石に、銀行が勧めてくれた投資信託!」
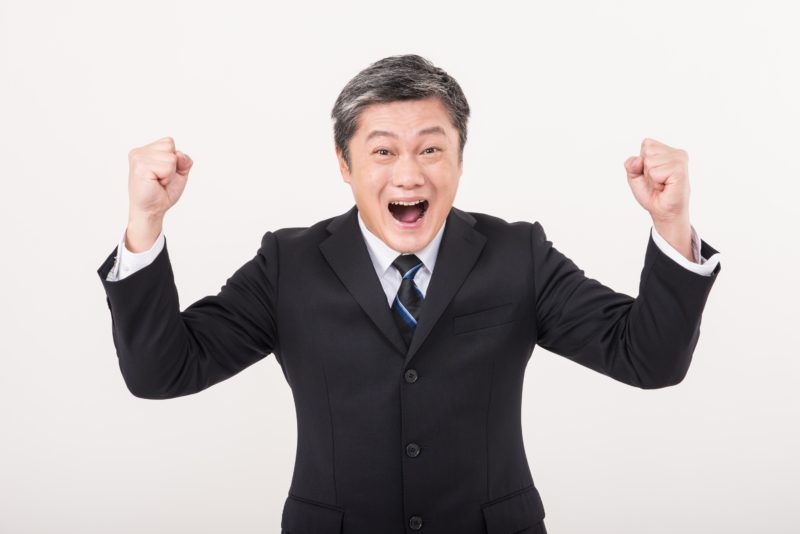
実は、配当金には2つのタイプがあります。
①普通配当金
②特別配当金
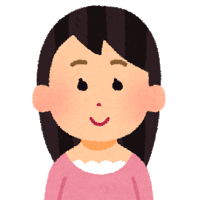
普通配当と特別配当は違うのですか??

はい、大きく違いますよ。

普通配当は運用益から分配するものなので、
そもそも利益が出なければ、配当はできません。

特別配当は、利益ではなく、自分が投資した元本から受取るのです。
つまり、毎月分配金が出ていても、それが普通か特別かでは大違いです。
特別分配と言うのは「元本の一部払戻し」なのです。
言葉を変えれば、自分の資産を切り崩しているのです。
だから、非課税なのです。
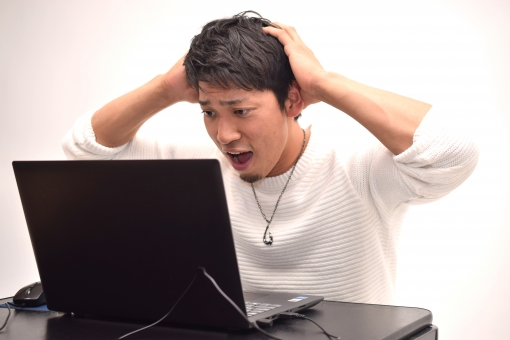
基準価額は高い方がいいのか?
基準価額とは、投資信託(ファンド)の値段です。
多くのファンドは、1万口当たりの金額で公表されます。
では、価額は高い方がいいのか?
それは、2つの角度から結論が違います。
①今すぐに換金して使いたい方は高い方が有利。
②長期的に増やしたい方は、必ずしも有利ではありません。
なぜなら、価額が高ければ、毎月買える「量」は少なくなります。
逆に価額が低い方が、買える「量」は多くなります。
積立投資は「量」を買い続け、増やしていく手法です。
ですので、途中は、下がった方が「量」を増やせます。
結論から言えば、長い目で見れば、相場に一喜一憂しない事です。
価額が上がる事も下がる事も悪い事ではないのです。
悪いのは、一方的に下がり続ける時です。

お付き合いで銀行から購入してませんか?
実は、個別相談を受けて多いのが、銀行から購入されている方が多いのです。
理由を聞くと、2つのパターンです。
①お付き合いで
②銀行を信用しています

では、銀行から投資信託を購入されている方の成績がどうなのか?
昨年から、金融庁の主導で、投資信託の成績表が公表されています。
つまり、どこの金融機関で買えば、利益が出ているのか。
一目瞭然に分かります。
上位は大手金融機関に属さない独立系です。
最高だったコモンズ投信では98%の方が含み益を出しています。
一方で、苦戦しているのが、中小証券と地銀です。
最下位の地銀では7割超が損失を出しております。

では、何故、銀行から購入された方の成績が悪いのか?
原因は何点か考えられます。
①投信の保有期間が短い。(回転売買)
②毎月分配型が多い。

投資の基本は何か?
長期・積立・分散
ちなみに、コモンズ証券は顧客の79%が積立投資で、2016年以前から継続的に投資している方の99%以上がプラスの収益を出しております。
つまり、会社の方針として、基本通りに、顧客にも説明をされている事が分かります。
私も銀行には10年間所属してました。
銀行の3大業務は預金・融資・為替でした。
特に、この中で重要だったのが中小企業向けの融資です。
ですので、融資を推進する為に、財務に関する研修は力を入れてました。
決算書を分析する力、中小企業の経営を分析する力は、銀行が一番です。
また、それが本業なのです。

以前は、投資信託も保険も、銀行の本来の業務ではありませんでした。
今、銀行がどういう目的で投資信託と保険を販売されているのか?
冷静に考えれば分かるはずです・・・。
それでも、銀行を信用して投資信託や保険を購入するお客様は多くおります。
その気持ちを裏切る行為は許されません。
言葉だけではなく、行動として「顧客本位」の営業を期待します。
iDeCoもつみたてNISAも投資信託です
投資信託は優れた金融商品です。
そして、この優れた投資信託に、非課税の制度をプラスしました。
それが、iDeCoであり、つみたてNISAです。
ですので、投資信託を始めるのであれば、まずは、iDeCoやつみたてNISAで検討をすべきです。

但し、金融機関により、取り扱っているファンドに制限もあります。
投資信託のデメリットは、ファンドが多すぎる事です。
多すぎる事で、特に初心者の方が戸惑ってしまい、結果的に行動ができない。
しかし、ファンドも大事なのですが、それ以上に大事な事があります。
それは3つ。
■早く、始める事
■長く続ける事
■途中で止めない事
では、どれ位の期間続ければいいのか?
推奨は15年以上です。
15年以上の期間があれば、よほど悪いファンド以外は利益が期待できます。
つみたてNISAはファンドの変更はできません。
しかし、iDeCoは変更が可能ですので、まずは始めましょう!
個別相談も受付しております。

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。




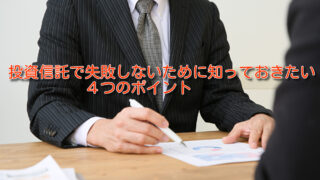


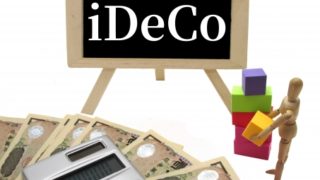














コメント